こんにちは、kanataです。
毎日の5分読書、続いています。
ガネーシャの課題として、死後に必要な手続きを調べる が出ました。
自分の死について考えるなんて、なんだか怖いなと以前は思っていたのですが、
『死について真剣に考えることで、今の生が輝く』
という言葉に触れてから、なるほどな、と
なんだか妙に冷静に、死について考えてみようと思ったことがあります。
今回は『おひとりさまが準備すべき死後手続き』を調べてみました。
・
・
・
「おひとりさまの場合、相続する人がいないから大丈夫」は勘違いでした
誰しも死後には何らかの財産が残ります。財産が残れば相続が発生します。
相続をスムーズに行うためには、遺言書を用意しておくのが終活の鉄則です。
配偶者・子どものいないおひとりさまの場合、遺言書を作成しておくのが賢明でしょう。
遺言書がなかったり、債権者や特別な縁故者が財産分与の申し立てをしない場合は、
最終的におひとりさまの財産は国庫に帰属する(国に引き渡す)ことになるようです。
・
・
・
「遺言書を書いておけば大丈夫」なのか?
遺言書といっても、民法で定められた正式な遺言書には、3種類あります。
1.自筆証書遺言
(専門家が立ち会わなくても作成できるが、法的な効力が認められないケースあり)
2.公正証書遺言
(作成時に公証人という専門家が関与する。手続きに手間や費用がかかるのが難点)
3.秘密証書遺言
(遺言の存在は知ってもらいつつ、内容を内密にできる。専門家が内容をチェックしないことや、財産の相続に関する内容に限定される。つまり、葬儀やお墓に関する希望、死後の様々な手続きに対する自分の意向については、遺言書と別に準備しておく必要がある。エンディングノートにできるだけ詳しく書いておくことが望ましいが、法的にしっかり効果を発揮するためには、手続きを代行する第三者を選定し、「死後事務委任契約」を結んでおくことが、万全の備えといえます。)
・
・
・
おひとりさまが終活で手配しておくべき6つのこと
相続だけでなく、自分の死後には数多くの手続きが待ち受けています。
残された人に迷惑をかけたくないという気持ちがあるなら、次の6つのポイントに関して、今のうちに手を打っておきましょう。
1.死亡届など役所への提出
2.葬儀の手配・執行
3.納骨・埋葬
4.電気・ガス・水道・電話・クレジットカードなどの清算・解約、デジタル遺品の処分
5.家財の片付け・形見分け
6.遺産の承継
・
・
・
1.死亡届など役所への提出
役所への事務手続きには、死亡届の提出や、戸籍関係の手続き、健康保険や年金の資格抹消申請などがあります。
これらは自分ではできないので、誰に届け出を頼むのか、事前に決めておきましょう。
・
2.葬儀の手配・執行
火葬の手配や葬儀をするならば、どのような葬儀にしてほしいかなどの希望も、エンディングノートにできるだけ詳しく書き残しておきましょう。
どの程度の予算で行い、誰に参列してほしいかも、はっきりと記しておきましょう。
・
3.納骨・埋葬
葬儀の手配・執行と同様です。
どのように埋葬してほしいかなど、生前にきちんと自分の意志を記しておくことで、残された人の負担を軽くすることができます。
・
4.電気・ガス・水道・電話・クレジットカードなどの清算・解約、デジタル遺品の処分
単なる事務的な処理と思いがちですが、多岐にわたる上に、清算を巡って金銭も絡んでくるので、誰にどのように対応してもらうのかをきちんと決めておきましょう。
SNSも、死後に削除作業を代行してもらえる人を確保しておくと安心です。
・
5.家財の片付け・形見分け
これは想像以上に重労働で時間も要します。
自分が元気なうちに自分自身で終活片付けを進めておくことが大事です。
自分の死後、誰にどのように頼むのかを明確にしておきましょう。
・
6.遺産の承継
遺言書が全面的に認められるとは限りませんが、自分の意志を明らかにしておくことで、無駄な争いをせずに済むかもしれません。
また、ペットを飼っている人は、引き取ってもらう先を決めておくことも必要です。
・
・
・
おひとりさまは「死後事務委任契約」という選択肢も
自分の身の回りの死後手続きは、できるだけ気心の知れた人に託したいと思うのが自然な感情でしょう。
しかし、うかつに家族や友人を代行者に選んでしまうと、大きな負担をかけてしまうことにもなりかねません。
迷惑をかけず円滑に手続きを進めたいと考えるなら、中立的な第三者に依頼し、生前にきちんと死後事務委任契約を結んでおくのが賢明でしょう。
この契約は、委任者が亡くなった後のさまざまな手続き(死後事務)を特定の第三者(個人もしくは法人)に代行してもらうという取り決めです。
死後事務委任は、遺言と異なり、死後のさまざまなことを取り決めることができます(ただし財産以外のことに限る)。
葬儀はどこで行いたい、埋葬はどうする、自分のペットはこの人に引き取ってほしいなど、事前に決めておくことができます。
そして自分の死後、受任者が速やかに死後事務を開始します。
個人間で委任する場合は、しっかりと希望を書き留めた上で伝えておきましょう。
・
・
・
死後事務委任契約の相談先は?
死後事務委任契約を結ぶ際に、委任先として税理士や司法書士と契約することもできますが、専門としている事務所が少なく相談しづらいことや、委任先によって料金が大きく異なるため、十分に検討する必要があります。
また葬儀会社など、死後事務業務を取り扱っている業者と契約することもできます。しかし、専門分野が各事業者で異なるため、複数の事業者に依頼する必要があるデメリットもあるでしょう。
一部の金融機関では、死後に発生する事務手続きをトータルでサポートするサービスを提供しているところもあります。
頼る相手がいない、また家族に迷惑をかけたくないと思っているおひとりさまは、自分の死後手続きのことを生前からしっかり考える必要があります。
「死後事務委任契約」を結ぶ、という選択肢もあることを知り、早いうちに手を打っておけば、もしものことを考えてやみくもに不安を抱くこともないでしょう。
・
・
・
以上、調べた内容から、
1.自分の財産について、自筆証書遺言 or 秘密証書遺言 を作成しておく。
自筆証書遺言の場合、認められなければ遺留分(民法で認められた最低限の相続財産の取得分)になったり、国に返す場合があること、
秘密証書遺言は自分で保管する必要があること、を理解しておく。
財産が大きくなれば公正証書遺言を検討。
+++
2.エンディングノートを作成、死後の手続きについて記載し(財産以外)、葬儀会社や金融機関などの業者に「死後事務委任契約の相談」をし、代行してもらう取り決めをする。
+++
3.自分の持ち物を定期的に整理整頓し、シンプルに暮らす
+++
私の場合、こんな感じですかね。
おひとりさまの私は、この世からの去り様をすっきりと身軽にしていきたいと思いました。
それでは/
kanata

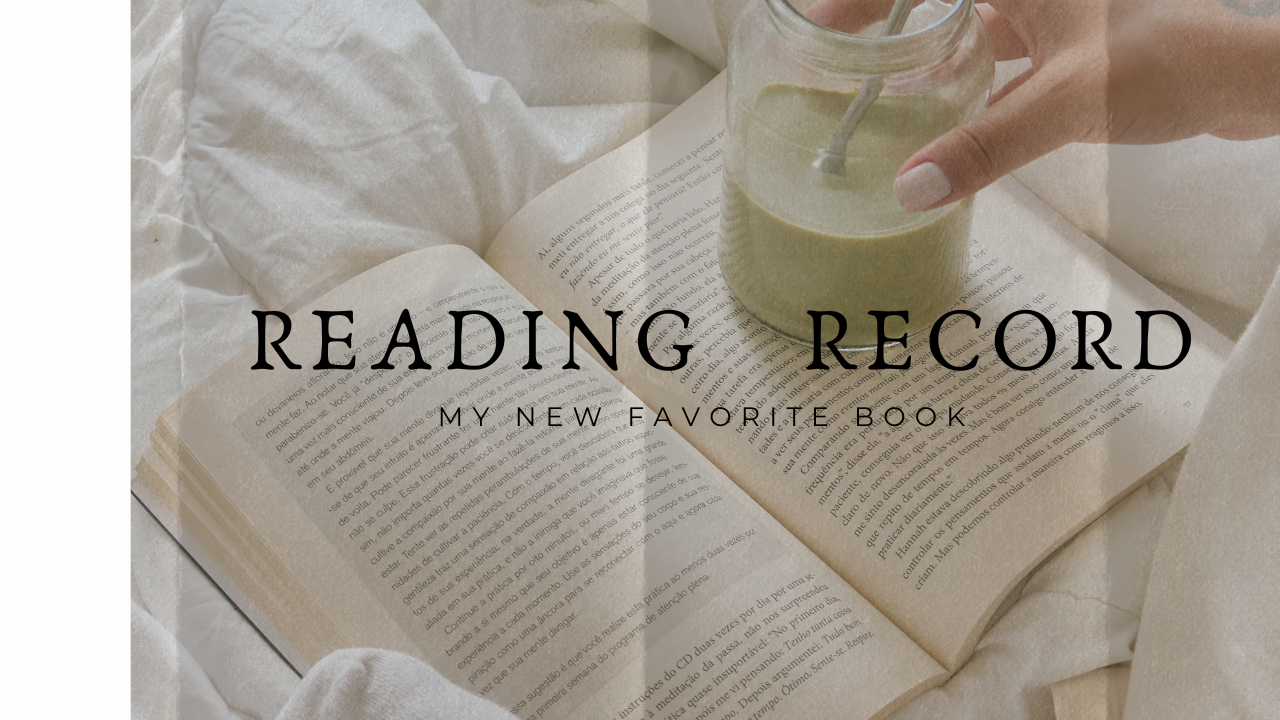

コメント